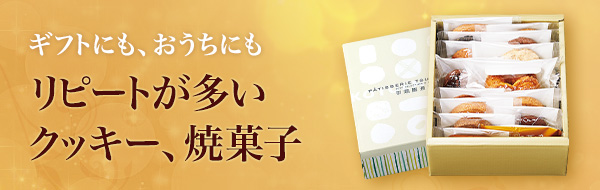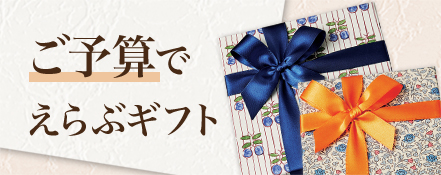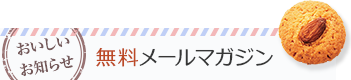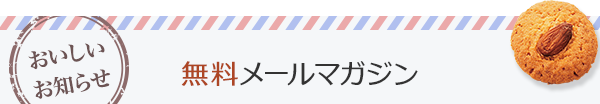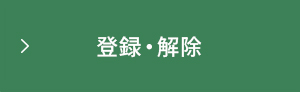ごきげんさん
「ごきげんさん」。それが子ども時代の私のあだ名でした。
運動会では、いつも観客席に手を振りながらニコニコと走っている。でも、他の子たちは10メートルも先にいて、私はいつもビリ。それでもあまりに機嫌よく堂々と走っているものだから「一等賞みたいだったよ」とよく言われたものです。
勉強ができたかといえば、それも全然だめ。通信簿はほとんど1か2だったので、周囲から「あいつはバカだ」と思われていたようですが、本人はいたって平気。周囲が感心するくらい、いつもどんなときでも楽しかったのです。

当時の私の家は、とんでもなく貧乏な状況でした。
TV番組でサバイバルゲーム(無人島で何も持たずに生活する)というのがありますが、あれをはるかに超える世界です。両親と早くに離れてしまった4人兄弟は母方のおばあちゃんに育てられ、現金収入がほとんどないなかで「食べ物は野生から見つけてくる」が当たり前の日々。
幸い私が生まれ育った宮崎県串間市は、ゆたかな海と山に面した土地で、術さえ身につければ、おいしい食材に恵まれる環境でした。運動会ではいつもビリの少年は、海に潜ってサザエ採りをさせると村一番。ピンピン飛び跳ねる伊勢海老を捕まえたり、海岸の断崖絶壁をのぼって牡蠣を採ってくるのも村一番でした。
それでも、他の子たちも魚や貝をとりたいから常に真剣勝負です。「津曲くん家は貧しいからどうぞ」なんて誰も譲ってくれない。自分の頭で考えて工夫して競争に勝たないと、家族の今日のご飯がまかなえない。何も賞品が出ない運動会とは訳がちがうのです。
おばあちゃんから「働かざるもの食うべからず」と言われていた私は、誰に教わるわけでもなく、食材確保のためにさまざまな技術を身につけていきました。
たとえば、海では潮の流れに逆らって泳ぐとすぐに疲れてしまう。逆に潮の流れに乗ればラクして進むことができます。それでも流され過ぎて必死になって戻ってきたこともありました。ある程度の収穫量を得るために1時間はかかるので、疲れたら海に浮かんで休む技術も身につけないといけない。常に生きるか死ぬかです。
そうかと思えば、ヒラメを取るときは無心が一番です。遠浅の海を一歩一歩進みながら、無欲になってモリを地面にドンドンとつき差していくと、ときどきシタビラメに命中しました。こちらがあまりにも淡々と近づいてきたので、ヒラメも「まさか!」と思っていたのでしょう。
今になって振り返ってみると、貧乏この上ない生活ではあったものの、採れたてのシタビラメや伊勢海老、旬の果物などどれも贅沢な素材ではあったなぁと思います。ひょっとしたら、菓子職人としての味覚はこの時に養われていったのかもしれません。

もう一つ、今でもよく思い出す光景があります。
当時、唯一の現金収入だったのが家畜の豚でしたが、人間用の食べ物も足りないほどですから、豚のエサも満足なものをあげられない。いも焼酎用に絞った芋のカスをもらってきてエサにするのですが、でんぷんカスというのはものすごく臭いので、豚も食べたがらないのです。
そこで、私はかまぼこ工場で魚の解体作業を手伝うことにしました。アルバイト代は出ないけれど、代わりに魚のアラなど不要な部分をもらえる。それを出汁にしてでんぷんカスを炊くと、豚がおいしそうに食べてくれるのです。これは大きな発見でした。それから毎朝、学校に行くまでの時間はかまぼこ工場で働くのが日課となります。
かまぼこ工場からの帰り道、魚のアラを積んだリヤカーを引いて、朝日が高くなっていく海辺の道をどんどんと進む。体はくたびれていたけれど「今日もたくさんもらえたから、ばあちゃんが喜ぶな。豚たちも喜んでくれるな」。真っ黒に日焼けした「ごきげんさん」の顔は、太陽を浴びながらピカピカと笑っていました。
-
 0120-221-071
0120-221-071 -
 0798-72-1846
0798-72-1846
- 営業時間:1階 午前10:00から午後6:00(生菓子、シュー、パイなど)
2階 午前9:00から午後6:00(クッキー、焼菓子) - 定休日:営業カレンダーをご確認ください
-
 0120-221-071
0120-221-071 -
 0798-72-1846
0798-72-1846
- 営業時間:1階 午前10:00から午後6:00(生菓子、シュー、パイなど)
2階 午前9:00から午後6:00(クッキー、焼菓子) - 定休日:営業カレンダーをご確認ください